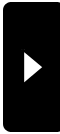2016年01月29日
『「水の素粒子」を見た眼が「太陽黒点」を語る』 あとがき
太陽には何故黒点があるのか。その謎が解けると、次は同時に何故光球を放つのか、という謎が生れました。その謎を教えているのもプラトンでした。プラトンは「火は四面体」という答を出しています。
「太陽の光を火」と捉えた私は、太陽の光が核から一〇本出て八本となる電磁力で、そして八本から六本に集約されている事が分かりました。
従って太陽は、六本の光が四面体で構成されているという事です。図に示した通り、六本の四面体の光の間隔は六〇度だから、三六〇度が光の表面になってしまった訳です。
水の素粒子(ひも)も「水は二十面体」とプラトンの言った通りでした。科学が聖なる哲人の言葉を取り入れるならば、最高の望遠鏡に更に哲人の目のフィルターを重ねて、より深く、鮮明に太陽を見る事が出来ると思います。
この事をもう一度、尊敬する科学界にお伝えしたいと決意して、申し述べました。これ以上はありません。ご覧くださいました皆々様に心から感謝します。誠にありがとうございました。
「太陽の光を火」と捉えた私は、太陽の光が核から一〇本出て八本となる電磁力で、そして八本から六本に集約されている事が分かりました。
従って太陽は、六本の光が四面体で構成されているという事です。図に示した通り、六本の四面体の光の間隔は六〇度だから、三六〇度が光の表面になってしまった訳です。
水の素粒子(ひも)も「水は二十面体」とプラトンの言った通りでした。科学が聖なる哲人の言葉を取り入れるならば、最高の望遠鏡に更に哲人の目のフィルターを重ねて、より深く、鮮明に太陽を見る事が出来ると思います。
この事をもう一度、尊敬する科学界にお伝えしたいと決意して、申し述べました。これ以上はありません。ご覧くださいました皆々様に心から感謝します。誠にありがとうございました。
2016年01月28日
『「水の素粒子」を見た眼が「太陽黒点」を語る』 八
一二.この長方形四面体が無数に無秩序に凝集して太陽は大きくなっている。光を出し終り、内部のエネルギーも全て吹き出し口から発散させ終ると、γ線が黒点を電離して、イオンと電子になる。
一三.電子一〇個は長方形第一軌道に二個で満員だからそこに安定し、残り八個の電子は全て第二軌道に収まる。最外殻の軌道の電子は八個で満員になるので、全ての電子の居場所は安定する。
一四.磁場の電磁力は、電磁波となる。電磁波は電子を貯める事も送電する事も出来る。行き先のないイオンの陽子一〇個と中性子一〇個を電磁波の中に取り込む。そして核内に送り込む。先に核の中に戻っていたニュートリノが、「強い力」で核の中に陽子と中性子を迎え入れる。
一五.時を経て、核が成長して、再び核の崩壊が始まる。初めのヘリウム五個の核融合で、循環の仕組を創り上げているから。出来上った太陽を研究しても、その因となっているヘリウム五個の正体は掴めない。
一六.ヘリウムの電子は水素であるから、太陽の電子を調べれば、水素のみしかない訳で、「太陽は水素から創られた」という勘違いをし易い。黒点は太陽の花なので、黒点を知る為、太陽の種を植えるところから、実の成るところまで話をしました。
一三.電子一〇個は長方形第一軌道に二個で満員だからそこに安定し、残り八個の電子は全て第二軌道に収まる。最外殻の軌道の電子は八個で満員になるので、全ての電子の居場所は安定する。
一四.磁場の電磁力は、電磁波となる。電磁波は電子を貯める事も送電する事も出来る。行き先のないイオンの陽子一〇個と中性子一〇個を電磁波の中に取り込む。そして核内に送り込む。先に核の中に戻っていたニュートリノが、「強い力」で核の中に陽子と中性子を迎え入れる。
一五.時を経て、核が成長して、再び核の崩壊が始まる。初めのヘリウム五個の核融合で、循環の仕組を創り上げているから。出来上った太陽を研究しても、その因となっているヘリウム五個の正体は掴めない。
一六.ヘリウムの電子は水素であるから、太陽の電子を調べれば、水素のみしかない訳で、「太陽は水素から創られた」という勘違いをし易い。黒点は太陽の花なので、黒点を知る為、太陽の種を植えるところから、実の成るところまで話をしました。
2016年01月27日
『「水の素粒子」を見た眼が「太陽黒点」を語る』 七
七.その光にはα線は青色で、γ線は赤色なので、二つが混じり合ってその光が放たれた時は白色光となる。
八.光の線が出来る訳は、長方形立方体の外殻の軌道に電子が八個あるから。核から二個一組で核子が逆スピンして、八個の電子の所に一直線に向うから、対称線が出来る。
九.八本の光が六本に集約される訳。八本の光の先端が陰、陽となっているから、六本のみが+、-で繋がり、二ヶ所は反発して繋がらず、太陽本体には対称的に二ヶ所の穴があく。この穴は余ったエネルギーを外部に吹き出す吹き出し口となる。
一〇.太陽本体から外部に放出する光の線は、六〇度の間隔で六本に集約される。表面に出る光は、ヘリウム中性子とγ線とα線から創られたもの。γ線は無限大の一直線で、α線は両手を広げた様に、斜めに左右に広がる線だから、三本の線となる。
一一.光球が創られた訳。プラトンの言った通り、「火は四面体」で、三本線上が表面で四面体となる。四面体が六〇度の間隔で六つ出来るから、三六〇度、太陽の全表面が白色光を放つという仕組になっている。尚、電子間は六〇度で釣り合って静止するから、これ以上外部から電磁力は働かない。
八.光の線が出来る訳は、長方形立方体の外殻の軌道に電子が八個あるから。核から二個一組で核子が逆スピンして、八個の電子の所に一直線に向うから、対称線が出来る。
九.八本の光が六本に集約される訳。八本の光の先端が陰、陽となっているから、六本のみが+、-で繋がり、二ヶ所は反発して繋がらず、太陽本体には対称的に二ヶ所の穴があく。この穴は余ったエネルギーを外部に吹き出す吹き出し口となる。
一〇.太陽本体から外部に放出する光の線は、六〇度の間隔で六本に集約される。表面に出る光は、ヘリウム中性子とγ線とα線から創られたもの。γ線は無限大の一直線で、α線は両手を広げた様に、斜めに左右に広がる線だから、三本の線となる。
一一.光球が創られた訳。プラトンの言った通り、「火は四面体」で、三本線上が表面で四面体となる。四面体が六〇度の間隔で六つ出来るから、三六〇度、太陽の全表面が白色光を放つという仕組になっている。尚、電子間は六〇度で釣り合って静止するから、これ以上外部から電磁力は働かない。
2016年01月26日
『「水の素粒子」を見た眼が「太陽黒点」を語る』 六
最後に太陽の真理を提供してご苦労されている科学界にお届けします。「太陽黒点」を研究する為に、太陽がどの様にして生れて、どのようにして育ち、循環しているのか、という本源から終りまでの流れを「水の素粒子」を見た眼が説明します。
一.初めは「重力」の働きによって、ヘリウム原子五個が集められる。
二.「重力」と「弱い力」と「強い力」と「電磁力」で核融合し、核をもつ長方形立方体の二重の軌道にトルクゼロになるように電子を配置した太陽本体が出来る。
三.「弱い力」と「強い力」と「電磁力」で核の崩壊が始まる。陽子は中性子+β線+ニュートリノに、中性子は中性子+β-線+ニュートリノになる。
四.核の陽子一〇個と軌道上の一〇個の電子とが+、-で電磁力をゼロにするので、この地点一〇個が黒点となる。β線はコロナを創る。この時、核からα線が出て、太陽本体を強固に創り上げる。磁場も電磁力をゼロにするから、太陽本体からコロナに達するまで、広範囲が黒く見える部分となる。
五.この働きは、ニュートリノが主導して働く。ニュートリノだから、核から電子の所まで逆スピンして、一直線の対称線を創り出す。そしてその後、ニュートリノだけが核に戻る。
六.次に核の中性子一〇個が、太陽本体の外側にある元のヘリウム原子五個が残した+孔一〇個と合体する。ここでも黒点一〇個が生れる。この時、核からγ線が出る。ニュートリノとγ線は、太陽本体の壁を容易く潜り抜ける。その時、軌道を飛び越える振動で強大なエネルギーが加算されて、そのエネルギーが加算されて、そのエネルギーが光となって外部に飛び出す。
一.初めは「重力」の働きによって、ヘリウム原子五個が集められる。
二.「重力」と「弱い力」と「強い力」と「電磁力」で核融合し、核をもつ長方形立方体の二重の軌道にトルクゼロになるように電子を配置した太陽本体が出来る。
三.「弱い力」と「強い力」と「電磁力」で核の崩壊が始まる。陽子は中性子+β線+ニュートリノに、中性子は中性子+β-線+ニュートリノになる。
四.核の陽子一〇個と軌道上の一〇個の電子とが+、-で電磁力をゼロにするので、この地点一〇個が黒点となる。β線はコロナを創る。この時、核からα線が出て、太陽本体を強固に創り上げる。磁場も電磁力をゼロにするから、太陽本体からコロナに達するまで、広範囲が黒く見える部分となる。
五.この働きは、ニュートリノが主導して働く。ニュートリノだから、核から電子の所まで逆スピンして、一直線の対称線を創り出す。そしてその後、ニュートリノだけが核に戻る。
六.次に核の中性子一〇個が、太陽本体の外側にある元のヘリウム原子五個が残した+孔一〇個と合体する。ここでも黒点一〇個が生れる。この時、核からγ線が出る。ニュートリノとγ線は、太陽本体の壁を容易く潜り抜ける。その時、軌道を飛び越える振動で強大なエネルギーが加算されて、そのエネルギーが加算されて、そのエネルギーが光となって外部に飛び出す。
2016年01月25日
『「水の素粒子」を見た眼が「太陽黒点」を語る』 五
宇宙の森羅万象には、原因が先にあって、その結果、物事が生れるという法則があります。その法則から見ると、「太陽黒点」を見る事は、太陽の成り立ちの途中に生れた「結果」として現われたものに過ぎません。現代の科学界ではその原因が明かされていません。原因とは「太陽黒点」は何から生れて、どの様に育って出来たのかを知る事です。
太陽を大木に譬えると、「太陽の種」が大地に植えられ、芽を出し、成長し、花が咲き、実をつけ、実を落として枯れた様になるけれども、時が来れば、また花が咲き、実を結ぶ、というものです。ここまで観察して、木全体の事が分かり、実の中に種が出来ている事や、その種が植えた時の種と同じ事を知る事が出来ます。
その意味で、「太陽黒点」は「太陽の花」です。「太陽の光球」は「太陽の実」です。ヘリウム五個の核融合の働きで、黒点も光球も法則通りに働いた結果出来上っています。だから、それが証拠となるのです。太陽の種が、ヘリウム五個である事は間違いありません。
どんな時代になろうとも、誰も知らなくとも、宇宙の真理が変る事はないのです。
太陽を大木に譬えると、「太陽の種」が大地に植えられ、芽を出し、成長し、花が咲き、実をつけ、実を落として枯れた様になるけれども、時が来れば、また花が咲き、実を結ぶ、というものです。ここまで観察して、木全体の事が分かり、実の中に種が出来ている事や、その種が植えた時の種と同じ事を知る事が出来ます。
その意味で、「太陽黒点」は「太陽の花」です。「太陽の光球」は「太陽の実」です。ヘリウム五個の核融合の働きで、黒点も光球も法則通りに働いた結果出来上っています。だから、それが証拠となるのです。太陽の種が、ヘリウム五個である事は間違いありません。
どんな時代になろうとも、誰も知らなくとも、宇宙の真理が変る事はないのです。
2016年01月24日
『「水の素粒子」を見た眼が「太陽黒点」を語る』 四
天文学者 カリフォルニア大学 ジョージ・フィッシャー
「“X線で明るく写る部分”は、「太陽の表面全体で散発的に生じています」
「黒点の集まった部分と、大量のX線が放射される活動域とは、ほぼ対応している事が知られています。しかし私の知る限り、それを正確に比較研究している人はいません」
・質問
「黒点の集まった部分と、表面全体で放射される明るい光の活動がほぼ対応しているという事は知られている、という事はつまりどういう事ですか?」
・M「水の素粒子を見た眼」が答える
「黒点が生れるのは核の崩壊により陽子が軌道の電子と合体して、電磁力を失ったからです。その次にほぼ同時に核から中性子が崩壊して、その時γ線が出ます。物体外の元の+孔に向ってそこを黒点にします。α線とγ線は、六本の光に集約されて、外に向って、四面体の光になって放射するのです。γ線は無限大の光が中心になって、その左右の斜めに二本のα線が束になって三本の光が放射するのです。三本は太陽表面で四面体となるので、それが球体を作るのです。α線は青色、γ線は赤色なので、二色が混ざり合って白色光となるので、太陽は白色光の球体となるのです。黒点と太陽表面から放射される活動とは、ほぼ同時というのは間違いありません。太陽の光球の成り立ちの図を示します」

「“X線で明るく写る部分”は、「太陽の表面全体で散発的に生じています」
「黒点の集まった部分と、大量のX線が放射される活動域とは、ほぼ対応している事が知られています。しかし私の知る限り、それを正確に比較研究している人はいません」
・質問
「黒点の集まった部分と、表面全体で放射される明るい光の活動がほぼ対応しているという事は知られている、という事はつまりどういう事ですか?」
・M「水の素粒子を見た眼」が答える
「黒点が生れるのは核の崩壊により陽子が軌道の電子と合体して、電磁力を失ったからです。その次にほぼ同時に核から中性子が崩壊して、その時γ線が出ます。物体外の元の+孔に向ってそこを黒点にします。α線とγ線は、六本の光に集約されて、外に向って、四面体の光になって放射するのです。γ線は無限大の光が中心になって、その左右の斜めに二本のα線が束になって三本の光が放射するのです。三本は太陽表面で四面体となるので、それが球体を作るのです。α線は青色、γ線は赤色なので、二色が混ざり合って白色光となるので、太陽は白色光の球体となるのです。黒点と太陽表面から放射される活動とは、ほぼ同時というのは間違いありません。太陽の光球の成り立ちの図を示します」

2016年01月23日
『「水の素粒子」を見た眼が「太陽黒点」を語る』 三
科学者 日本科学技術振興財団 科学技術館(アメリカ・エクスプロラトリアムにより制作されたものを翻訳しました)
恒星物理学者 デビッド・ディアボーン
「地球の磁場のやや深いところに飛び込んだ太陽のエネルギー粒子は、地球の磁場に取り込まれて、北極と南極の間を行ったり来たりします。その結果、美しいオーロラが発生するという訳です」
・質問
「太陽のエネルギーは、表面から放射される光だけではないのですか?それが地球の北極と南極の間を行ったり来たりするというからには、地球には内部に北極と南極を貫通する穴でもあるのですか?」
・M「水の素粒子を見た眼」が答える
「太陽は黒点を作る時、同時に光球が発生します。その時、太陽内部で余ったエネルギーが、外に向って吹き出す出口があります。太陽を貫通して、両極二ヶ所の吹き出し口があります。地球にも同じ星の仲間ですから、仕組は同じだと思います。長方形の四面体の物体からは初め八方に光の線が出ます。八本の内、電磁力で結ばれる所は六ヶ所だけで、二ヶ所は電磁力が反発し、反発力で隣の線の+、-が結ばれ吸収されるから、六本の光の線になるのです。その結果太陽には二ヶ所、核から左右に貫通した穴が出来るのです。太陽の吹き出し口の図を示します」

恒星物理学者 デビッド・ディアボーン
「地球の磁場のやや深いところに飛び込んだ太陽のエネルギー粒子は、地球の磁場に取り込まれて、北極と南極の間を行ったり来たりします。その結果、美しいオーロラが発生するという訳です」
・質問
「太陽のエネルギーは、表面から放射される光だけではないのですか?それが地球の北極と南極の間を行ったり来たりするというからには、地球には内部に北極と南極を貫通する穴でもあるのですか?」
・M「水の素粒子を見た眼」が答える
「太陽は黒点を作る時、同時に光球が発生します。その時、太陽内部で余ったエネルギーが、外に向って吹き出す出口があります。太陽を貫通して、両極二ヶ所の吹き出し口があります。地球にも同じ星の仲間ですから、仕組は同じだと思います。長方形の四面体の物体からは初め八方に光の線が出ます。八本の内、電磁力で結ばれる所は六ヶ所だけで、二ヶ所は電磁力が反発し、反発力で隣の線の+、-が結ばれ吸収されるから、六本の光の線になるのです。その結果太陽には二ヶ所、核から左右に貫通した穴が出来るのです。太陽の吹き出し口の図を示します」

2016年01月22日
『「水の素粒子」を見た眼が「太陽黒点」を語る』 二
天文学者 カリフォルニア大学 ジョージ・フィッシャー
「黒点が黒く見えるのは、周囲よりも温度が低いためです。強力な磁場によって、太陽内部で起る対流による熱の移動が妨げられているのです。この磁場は太陽表面よりも下で形成され、コロナにまで達しています」
・質問
「黒点は何故温度が低いのですか?太陽内部で起る対流に妨げられているのですか?」
・M「水の素粒子を見た眼」が答える
「黒点が黒く見えるのは、周囲より温度が低いためというのはその通りです。何故温度が低くなったのかといえば、太陽は中心に核のある長方形立方体の二重の軌道をもつ物体です。この物体が核融合を繰り返しているのです。対流に妨げられたものではありません。核の崩壊により、核内の陽子のプラス電子が、軌道のマイナス電子と合体して、+、-、ゼロとなり、電磁力を消してしまうのです。電磁場もそれに伴って電磁力が消えるので、温度が下がり、光を出さないので、軌道の明るさの中で、目立って黒く見えるのです。磁場は広範囲で、コロナにまで達しているというのはその通りです。太陽黒点の図で開示します」

「黒点が黒く見えるのは、周囲よりも温度が低いためです。強力な磁場によって、太陽内部で起る対流による熱の移動が妨げられているのです。この磁場は太陽表面よりも下で形成され、コロナにまで達しています」
・質問
「黒点は何故温度が低いのですか?太陽内部で起る対流に妨げられているのですか?」
・M「水の素粒子を見た眼」が答える
「黒点が黒く見えるのは、周囲より温度が低いためというのはその通りです。何故温度が低くなったのかといえば、太陽は中心に核のある長方形立方体の二重の軌道をもつ物体です。この物体が核融合を繰り返しているのです。対流に妨げられたものではありません。核の崩壊により、核内の陽子のプラス電子が、軌道のマイナス電子と合体して、+、-、ゼロとなり、電磁力を消してしまうのです。電磁場もそれに伴って電磁力が消えるので、温度が下がり、光を出さないので、軌道の明るさの中で、目立って黒く見えるのです。磁場は広範囲で、コロナにまで達しているというのはその通りです。太陽黒点の図で開示します」

2016年01月21日
『「水の素粒子」を見た眼が「太陽黒点」を語る』 一
科学者 日本科学技術振興財団 科学技術館(アメリカ・エクスプロラトリアムにより制作されたものを翻訳しました)
「太陽表面上には黒い斑点があって、収縮や膨張を繰り返しながら移動します。斑点の中には直径が八〇,〇〇〇kmに及ぶものもあります。この奇妙でダイナミックな現象が「太陽黒点」です」
・質問
「太陽は光の球体なのに、光の表面上に黒い絵が書けるのですか?光の表面のその部分が黒いのですか?」
・M「水の素粒子を見た眼」が答える
「太陽表面上に黒点があるのではなくて、黒点が見えるという事は、太陽の光の中心部に黒点を作る物体があるから、光が透視して表面にあるように黒く見えるのです。太陽の中心には、核をもち二重の長方形立方体の軌道をもった太陽の本体があります。本体のその軌道上で起る電子が、核の崩壊によって電磁力をゼロにするから、ゼロになった地点と磁場が黒くなります。太陽は、太陽分子の集合体だから、黒点はあちこちで出来るし、核は崩壊したままでなく再生しますから、その時黒点は消えて見えなくなるのです。太陽の骨組みと電子の配置図を示します」

「太陽表面上には黒い斑点があって、収縮や膨張を繰り返しながら移動します。斑点の中には直径が八〇,〇〇〇kmに及ぶものもあります。この奇妙でダイナミックな現象が「太陽黒点」です」
・質問
「太陽は光の球体なのに、光の表面上に黒い絵が書けるのですか?光の表面のその部分が黒いのですか?」
・M「水の素粒子を見た眼」が答える
「太陽表面上に黒点があるのではなくて、黒点が見えるという事は、太陽の光の中心部に黒点を作る物体があるから、光が透視して表面にあるように黒く見えるのです。太陽の中心には、核をもち二重の長方形立方体の軌道をもった太陽の本体があります。本体のその軌道上で起る電子が、核の崩壊によって電磁力をゼロにするから、ゼロになった地点と磁場が黒くなります。太陽は、太陽分子の集合体だから、黒点はあちこちで出来るし、核は崩壊したままでなく再生しますから、その時黒点は消えて見えなくなるのです。太陽の骨組みと電子の配置図を示します」

2016年01月20日
『「水の素粒子」を見た眼が「太陽黒点」を語る』 序文 四
昨年中は「水の素粒子」の話。今年初頭から「太陽の黒点」の話。何の為にそこまでやるのか、それは未知の世界を知った者が、人々に知らせるという事が、人を救うという事であると思うからです。その意味で、太陽の光の色の事を初めに語りました。
これから、「水の素粒子」を見た眼が「太陽黒点」を語る、というその方法は、次の様にしたいと思います。「太陽黒点」の話は、諸々の学者の話はいっぱいあります。初めは実在の科学者の談話を述べます。これに対して、質問者Aが質問する、それに対して「水の素粒子を見た眼」が図面に書いて説明する、という形で進めていきます。
これから、「水の素粒子」を見た眼が「太陽黒点」を語る、というその方法は、次の様にしたいと思います。「太陽黒点」の話は、諸々の学者の話はいっぱいあります。初めは実在の科学者の談話を述べます。これに対して、質問者Aが質問する、それに対して「水の素粒子を見た眼」が図面に書いて説明する、という形で進めていきます。